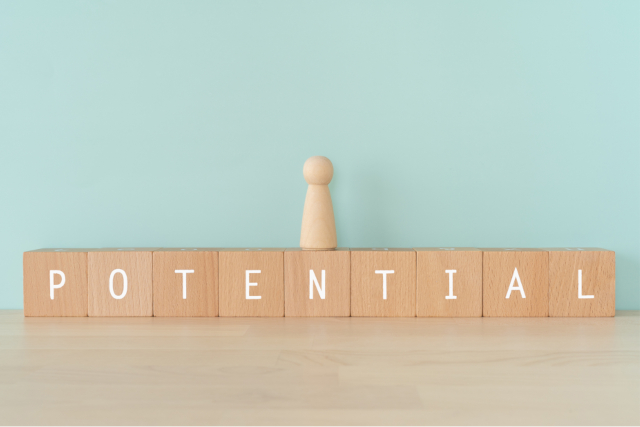2025年11月19日
カテゴリ:デジタルトランスフォーメーション

健康経営とは、企業の成長に不可欠な従業員の健康を経営的な視点で考え、戦略的に実践することを意味します。
この記事では、健康経営の基本的な意義や目的、そしてなぜ今、日本の多くの会社で注目されているのか、その背景を分かりやすく解説します。
企業が健康経営に取り組むメリットや、具体的な取り組み事例も紹介するため、自社で健康経営を推進する際の参考にしてください。
INDEX
健康経営とは従業員の健康を投資と捉える経営手法のこと
健康経営の定義は、従業員の健康保持・増進をコストとしてではなく、企業の持続的な成長を支えるための投資と捉える経営理念に基づきます。
この考え方の始まりは、従業員の活力向上が企業の生産性を高めるという米国の研究にあります。
近年では、個人の身体的・精神的・社会的な幸福を指すウェルビーイング経営とも関連付けられ、ヘルスケアの領域を超えて、企業のサステナビリティに不可欠な要素として認識されています。
今、健康経営が重要視される3つの社会的背景
現代の日本において、健康経営が重要視される理由には、複数の社会的な問題点が関係しています。
特に、労働人口の減少や社会保障費の増大といったマクロな問題は、企業経営に直接的な影響を及ぼします。
また、働き方の多様化に伴い、従業員の健康に対する意識も変化しており、労働安全衛生の観点からも、企業が従業員の心身の健康に対し、積極的に関与する必要性が高まっています。
背景1:少子高齢化による労働人口の減少
日本では少子高齢化が急速に進行しており、多くの産業で労働力不足が深刻な課題となっています。
限られた人材で企業が成長を維持するためには、従業員一人ひとりが心身ともに健康で、高いパフォーマンスを発揮し続ける環境を整えることが不可欠です。
従業員の健康を維持・増進させることは、個々の労働生産性を高め、組織全体の活力を向上させることにつながります。
優秀な人材の確保と定着が企業の競争力を左右する現代において、健康経営は重要な経営戦略の一つといえます。
背景2:社会保障費の増大と企業の負担
社会保障費は年々増加傾向にあり、それに伴って企業が負担する健康保険料の割合も上昇し続けています。
従業員が健康であれば、医療機関を受診する機会が減少し、結果として医療費の適正化に貢献します。
これは、企業の保険料負担の軽減に直結するため、企業の利益確保の観点からも重要です。
従業員の健康増進への投資は、将来的な医療費負担を抑制する費用対効果の高い取り組みであり、企業の予算計画においても無視できない要素となっています。
背景3:働き方改革による従業員の健康意識の高まり
「働き方改革」の推進により、長時間労働の是正や柔軟な働き方が社会に浸透し、従業員自身の健康に対する意識、すなわちヘルスリテラシーが高まっています。
多くの人がワークライフバランスを重視するようになり、自身の幸福や満足度、すなわちウェルビーイングを追求する傾向が強まりました。
こうした価値観の変化を受け、企業には従業員が心身ともに健康で、いきいきと働ける環境を提供することが求められています。
従業員の健康をサポートする姿勢は、企業の魅力向上にも直結します。
企業が健康経営に取り組むことで得られる4つのメリット
企業が健康経営に投資することは、単に費用がかかるだけでなく、組織に多くのプラスの効果をもたらします。
従業員の生産性向上や人材の定着といった直接的なメリットに加え、企業のブランドイメージ向上という間接的な効果も期待できます。
これらのメリットは相互に関連し合い、企業の持続的な成長を支える基盤となります。
メリット1:従業員の生産性が向上する
従業員の心身のコンディションが良好であることは、業務パフォーマンスの向上に直接的に作用します。
体調不良による欠勤、いわゆるアブセンティーズムの減少はもちろん、出社していても心身の不調によって本来の能力を発揮できない状態(プレゼンティーズム)の改善が見込めます。
健康的な状態は、仕事に対する活力や熱意であるワークエンゲージメントを高め、従業員のモチベーション向上にも寄与します。
結果として、組織全体の生産性が高まり、企業の業績向上につながっていきます。
メリット2:離職率が低下し優秀な人材が定着する
従業員の健康に配慮した職場環境や制度は、従業員満足度や企業への愛着、すなわちエンゲージメントを高める重要な要素です。
従業員が心身ともに健康で働き続けられる環境は、健康問題を理由とした離職を防ぎ、離職率の低下に貢献します。
特に、長期的なキャリア形成を考える優秀な人材にとって、企業が従業員の健康を重視する姿勢は大きな魅力となります。
結果として、貴重な人材の流出を防ぎ、組織全体の競争力を維持・強化することが可能になります。
メリット3:採用活動で企業イメージが向上する
健康経営に積極的に取り組む姿勢は、「従業員を大切にするホワイトな企業」というポジティブな印象を社外に与えます。
これは採用活動において強力なアピールポイントとなり、優秀な人材の獲得競争において優位に立つリクルート効果が期待できます。
特に、自身の働きがいやワークライフバランスを重視する求職者にとって、企業の健康への配慮は重要な判断基準の一つです。
リクルートサイトや会社説明会で具体的な取り組みを紹介することで、他社との差別化を図り、採用力の強化につなげることが可能です。
メリット4:企業のブランド価値が高まる
健康経営優良法人などの認定を受けることは、企業の社会的な評価を高め、ブランドイメージの向上に大きく寄与します。
顧客や取引先からの信頼を獲得しやすくなり、営業活動においても有利に働く場合があります。
また、企業の取り組みがニュースとしてメディアで紹介されたり、自社のホームページで積極的に情報発信したりすることで、企業のサステナビリティへの姿勢を広く社会にアピールできます。
これは、ESG投資を重視する投資家からの評価にもつながり、企業価値全体の向上に貢献するのです。
健康経営を社内に導入するための5つのステップ
健康経営を始めたいと考えても、何から着手すべきか難しいと感じるかもしれません。
しかし、確立されたフレームワークに沿って段階的に進めることで、効果的な推進が可能です。
ここでは、社内で健康経営を推進するための組織体制の構築から具体的な進め方までを、5つのステップで解説します。
自社だけで進めるのが困難な場合は、外部のコンサルタントやアドバイザーといった専門家のコンサルティングを活用することも有効な選択肢です。
ステップ1:経営層が健康経営を宣言する
健康経営を全社的な取り組みとして浸透させるには、経営トップの強い意志とリーダーシップが不可欠です。
まず、社長や担当役員が、従業員の健康を重要な経営課題と位置づけ、会社として積極的に支援していく方針を「健康宣言」として社内外に明確に表明します。
この宣言は、取り組みが単なる福利厚生ではなく、経営戦略の一環であることを全従業員に示すものです。
方針を明文化し、ホームページや社内報などを通じて発信することで、全社的な協力体制を築くための基盤ができます。
ステップ2:推進担当者や部署を設置する
経営トップによる健康宣言を受け、次に具体的な推進体制を構築します。
人事部や総務部が中心となるケースが多いですが、産業医や保健師、各部署の代表者などをメンバーとする専門部署や部門横断のワーキンググループを設置すると、より効果的に活動を進められます。
推進担当者の役割を明確にし、健康課題の把握、計画の策定、施策の実行、効果検証といった一連のプロセスを遂行する体制を整えます。
この推進体制が、継続的な取り組みの要となります。
ステップ3:自社の健康課題を明確にする
効果的な施策を立案するためには、自社の従業員がどのような健康課題を抱えているかを正確に把握することが出発点となります。
定期健康診断の結果やストレスチェックのデータ、時間外労働時間などを分析し、客観的なデータに基づいて課題を可視化します。
さらに、従業員に生活習慣や働きがいに関するアンケートやサーベイを実施し、潜在的な健康リスクやニーズを把握します。
労働安全衛生法で定められた義務を遵守するだけでなく、自社特有の課題を特定することが重要です。
ステップ4:具体的な目標と計画を立てる
把握した健康課題を基に、具体的で測定可能な目標を設定します。
例えば、「定期健康診断の受診率100%を維持する」「ストレスチェックの集団分析結果における高ストレス者比率を前年比5%低下させる」といった目標が考えられます。
目標を達成するための具体的な行動計画を策定し、実施する施策のスケジュールや担当者を明確にします。
また、取り組みの成果を客観的に評価するための指標(評価項目)もこの段階で定めておき、計画の進捗を定期的に確認できる仕組みを作ります。
ステップ5:施策を実行し効果を検証する
策定した計画に基づき、健康に関する教育セミナーの開催や運動機会の提供、食事改善のサポートなど、具体的な施策を実行します。
施策の実施後は、その効果を定期的に評価することが不可欠です。
設定した目標や指標の達成度をデータで確認し、従業員へのアンケートで満足度や意識の変化を測定します。
評価結果はレポートとしてまとめ、経営層や従業員にフィードバックします。
この検証結果を基に、次期の計画や施策の改善提案を行い、PDCAサイクルを回していくことが継続的な成果につながります。
明日から始められる健康経営の具体的な取り組み事例
健康経営の取組は多岐にわたり、企業規模や業種によって適した内容は異なります。
ここでは、比較的始めやすい具体的な取り組み内容を、様々な企業の取組事例を交えて紹介します。
近年は、健康管理をサポートするクラウドサービスやマネジメントツール、外部のソリューションも充実しており、これらを活用するのも一つの方法です。
身体の健康に関する取り組み事例
従業員の身体的な健康を支えることは、健康経営の基本です。
始業時のラジオ体操や、部署対抗のウォーキングイベントなど、日常的に運動習慣を促す施策は手軽に始められます。
また、社員食堂で栄養バランスの取れたヘルシーメニューを提供したり、朝食を無料で配布したりすることも食事面での有効なサポートです。
禁煙外来の費用補助や、ウェアラブルデバイスを配布して睡眠や活動量を管理する取り組みも効果が期待できます。
定期健康診断の受診率100%を目指すだけでなく、疾病の早期発見・予防のための二次健診受診勧奨も重要です。
心の健康(メンタルヘルス)に関する取り組み事例
身体の健康と同様に、心の健康、すなわちメンタルヘルスの維持・向上も非常に重要です。
メンタルヘルス対策の第一歩として、法律で義務付けられているストレスチェックを適切に実施し、高ストレス者へのフォロー体制の構築が求められます。
産業医や保健師といった産業保健スタッフによる相談窓口を設け、従業員が気軽に悩みを相談できる環境を整えることも大切です。
また、管理職を対象としたラインケア研修や、全従業員向けのセルフケア研修を実施し、メンタル不調を未然に防ぐ知識を組織全体で共有します。
さらに、ハラスメント防止に関する研修も、健全な職場風土の醸成に不可欠です。
職場環境の改善に関する取り組み事例
従業員が心身ともに健康で、安全に働ける職場環境の整備は健康経営の土台となります。
長時間労働の是正や有給休暇の取得促進は、従業員の疲労回復を促し、労働災害のリスクを低減させます。
また、高さが調節できるデスクやリフレッシュスペースをオフィスに設けるなど、快適で効率的なワーキング環境を整えることも有効な取り組みです。
さらに、育児や介護といった家庭の事情と仕事を両立できるよう、短時間勤務やテレワークなどの両立支援制度を充実させることも、多様な人材が長く活躍できる組織づくりに貢献します。
コミュニケーション活性化に関する取り組み事例
職場内の円滑なコミュニケーションは、従業員のストレス軽減やチームワークの向上に寄与します。
社内サークル活動への補助金制度や、部署の垣根を越えた交流イベントの開催は、従業員同士のつながりを深める良い機会となります。
また、ハラスメントや人間関係の悩みを匿名で相談できる窓口を設置し、従業員が安心して相談できる体制を整えることも重要です。
労働組合と連携した健康セミナーの開催や、社内報などの通信媒体を活用して他部署の取り組みを紹介することも、組織の一体感を醸成し、風通しの良い職場づくりにつながります。
国が推進する健康経営の認定制度を知ろう
国や地方自治体は、企業の健康経営への取り組みを促進するため、様々な顕彰制度を設けています。
これらの認定を取得すると、認定ロゴマークの使用が許可され、企業のイメージアップや採用活動でのアピールにつながります。
さらに、一部の金融機関や自治体では、融資における金利優遇や、公共調達における評価での加点、補助金の対象となるなどのインセンティブが用意されています。
経済産業省が認定する「健康経営優良法人認定制度」
「健康経営優良法人認定制度」は、経済産業省が制度設計を行い、日本健康会議が認定する、健康経営に関する代表的な顕彰制度です。
2016年度に創設され、企業の規模に応じて「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」の2つの区分があります。
特に優れた取り組みを行う法人として、大規模法人部門の上位500社は「ホワイト500」、中小規模法人部門の上位500法人は「ブライト500」として認定されます。
申請は例年8月下旬から10月頃にかけて行われ、申請書は経済産業省のウェブサイトで公開されます。
加入している協会けんぽや健康保険組合を通じて提出し、認定期間は1年間で毎年更新が必要です。
東京証券取引所の上場企業が対象の「健康経営銘柄」
「健康経営銘柄」は、経済産業省と東京証券取引所が共同で、東京証券取引所に上場している企業の中から選定する制度です。
従業員の健康管理を経営的な視点で捉え、戦略的に実践している企業を、投資家にとって魅力ある投資先として紹介することを目的としています。
原則として1業種につき1社が選定され、選定された企業は長期的な企業価値向上が期待できると評価されます。
この銘柄に選定されることは、投資家への強力なアピールになるだけでなく、企業のブランド価値向上にも大きく貢献します。
まとめ
本記事のまとめとして、健康経営の重要性を改めて確認します。
従業員の健康を経営的な資源と捉え、戦略的に投資を行うことは、生産性の向上、人材の定着、ひいては企業価値の向上という形で企業にリターンをもたらします。
少子高齢化による労働力不足や働き方の多様化といった社会環境の変化に対応し、企業が持続的に成長を遂げる上で、健康経営への取り組みはもはや不可欠です。
まずは自社の現状と課題を正確に把握し、経営トップの強いリーダーシップのもと、全社一丸となって推進していくことが成功への道筋となります。
注目のコラム記事
よく読まれている記事
新着記事
PICKUP