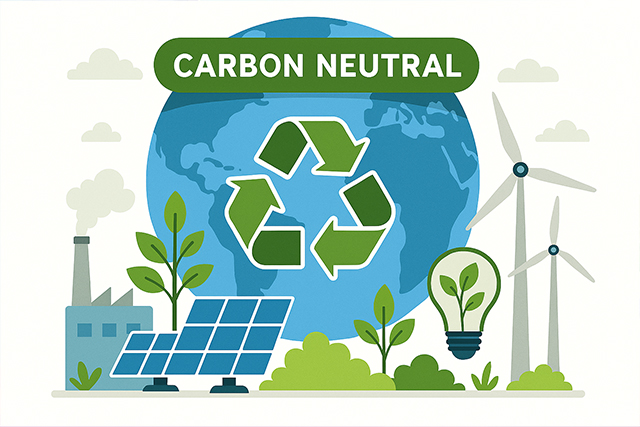2025年11月06日
カテゴリ:財務会計

管理会計とは、企業が経営上の意思決定を行うために活用する社内向けの会計情報のことです。
本記事では、管理会計の基礎的な意味や知識から、その必要性、そして財務会計との違いまで、経営に役立つ基本についてわかりやすく説明します。
管理会計を導入することで、企業は自社の状況を正確に把握し、戦略的な経営を実現することが可能になります。
INDEX
管理会計とは経営判断に役立てるための社内向け会計
管理会計は、経営者や各部門のマネージャーが自社の経営状況を把握し、経営方針や事業戦略といった意思決定に役立てることを目的とした会計です。
そのため「マネジメント会計」とも呼ばれ、その役割は社内向けの経営管理に特化しています。
企業の目標達成に向けた業績測定や評価、課題の分析など、経営の羅針盤として機能します。
法律による定めがないため、企業は自社の方針に合わせて、役立つ情報を自由な形式で報告・分析し、内部マネジメントを管理するために活用します。
管理会計と財務会計の違いを比較
企業会計は、社内向けの管理会計と社外向けの財務会計に大別されます。
両者は目的や報告対象、作成ルールなどが大きく異なります。
財務会計は、株主や債権者などの利害関係者に対して経営成績や財政状態を報告するために、法律や会計基準に則って作成されるもので、制度会計とも呼ばれます。
このセクションでは、管理会計と財務会計の違いを3つの観点から比較し、それぞれの役割を明確にします。
報告する相手が社内か社外か
最も大きな違いは、会計情報を提供する相手です。
管理会計の報告相手は、経営者や取締役、各部門の責任者といった社内の関係者に限定されます。
その目的は、自社の経営課題の把握や改善策の検討、将来の経営戦略の立案など、内部での意思決定にあります。
一方、財務会計は、株主や投資家、金融機関、取引先、税務署といった社外の利害関係者が報告の対象です。
企業の財政状態や経営成績を外部に公表し、利害関係者の投資判断や与信判断に資することを目的としています。
そのため、管理会計で用いる報告書や帳票は社内で自由に設計できます。
作成ルールが任意か法律で定められているか
財務会計は、株主や投資家などの利害関係者が企業の状況を公平に比較・判断できるよう、会社法や金融商品取引法、税法といった法律に基づき、厳格な会計基準に則って作成する義務があります。このルールに従わない場合、罰則が科されることもあります。
これに対して、管理会計には法的な作成義務や統一された基準は存在しません。
どのようなデータを収集し、どう分析・活用するかは完全に企業の自由です。各企業が自社の経営課題や目的に合わせ、最も効果的だと判断する方法や要件で自由にルールを設計できる点が大きな特徴です。
対象となる情報の範囲(過去・現在・未来)
財務会計が主に取り扱うのは、過去の経営活動の結果を示す情報です。
決算期に作成される損益計算書や貸借対照表は、会計期間における確定した実績値をまとめたものであり、過去の事実に基づいています。
一方で、管理会計は過去の実績データに留まらず、現在の状況分析や、将来の予測といった未来志向の情報も重視します。
例えば、事業計画の策定、来期の売上予測、設備投資の効果シミュレーションなど、未来の経営判断に直接関わる情報を扱います。
この点において、過去の決算報告を中心とする財務会計とは大きく異なります。
企業が管理会計を導入する3つの目的
多くの企業が管理会計を導入するのは、経営をより良い方向へ導くことを含めた、明確な目的があるからです。
そのため、単に数字を管理するだけでなく、そのデータを活用して迅速な意思決定を支援し、各部門の業績を正しく評価して改善へとつなげます。
さらに、会社全体で目指すべき経営目標の達成度合いを可視化することも重要な目的です。
管理会計の導入は、感覚的な経営から脱却し、データに基づいた戦略的な経営を実現するための基盤となります。
迅速な意思決定をサポートする
変化の激しい現代の経営環境において、迅速で的確な意思決定は企業の競争力を左右します。
管理会計は、部門別・製品別の損益状況やコスト構造など、経営判断に必要な詳細なデータをタイムリーに提供する役割を担います。
例えば、採算が合わない事業からの撤退や、新たな設備投資の実行、新製品の価格設定など、重要な局面で客観的な数値に基づいた、根拠のある判断を下すことが可能になります。
これにより、経営者は勘や経験だけに頼ることなく、データに裏付けられたスピーディな意思決定を行えるようになります。
業績を正しく評価して改善につなげる
管理会計を活用することで、企業全体の業績だけでなく、事業部、製品、店舗といったより細かい単位での業績を客観的に評価できます。
各セグメントの収益性やコスト構造を詳細に分析することにより、どの部門が収益に貢献しており、どこに問題や課題が潜んでいるのかを具体的に特定可能です。
これにより、好調な部門の強みをさらに伸長させる戦略や、不振部門の課題を解決するための具体的な改善策を立案することが容易になります。
数値に基づいた正確な現状把握が、的確な改善アクションを導き出します。
経営目標の達成度合いを明確にする
企業が設定した売上高や利益率といった経営目標に対し、現状がどの地点にあるのか、その進捗度合いを可視化することも管理会計の重要な目的です。
例えば、予実管理を通じて予算と実績の差異を定期的に把握し、目標とのギャップがなぜ生じているのかを分析します。
この分析結果をもとに、目標達成に向けた具体的なアクションプランの修正や追加策の検討が可能になります。
KPIのような具体的な指標を設定し進捗を追うことで、組織全体が目標達成に向けて一丸となって取り組む意識を醸成します。
管理会計を導入して得られる4つのメリット
管理会計の導入は、企業経営に多くの利点をもたらします。
代表的な管理会計のメリットとして、経営状況をリアルタイムで把握できること、事業部ごとの課題が明確になること、コスト削減のポイントが見つけやすくなること、そして社員の経営参画意識を高められることの4つが挙げられます。
これらのメリットは、企業の収益性向上や組織力強化に直接的に貢献し、持続的な成長を支える基盤となります。
会社の経営状況をリアルタイムで把握できる
財務会計が提供する情報は年次や四半期ごとの確定値が中心であり、経営者が現状を把握するまでには時間がかかります。
一方、管理会計では月次や週次、場合によっては日次でデータを集計・分析するため、常に最新の経営状況を把握することが可能です。
売上や利益の進捗、コストの発生状況などをリアルタイムで確認できることで、問題の早期発見と迅速な対応が可能になります。
経営の舵取りにおいて、現状に対する正確な見方を常に持てることは、競争上の大きな優位性となります。
事業部や部署ごとの課題が明確になる
会社全体の財務諸表を見るだけでは、どの事業や部署が収益を牽引し、どの部分が業績の足かせとなっているのかを判断するのは困難です。
一方で管理会計では、事業部、製品グループ、地域といった任意のセグメントに財務情報を区分し、セグメント別の損益分析を行います。
この詳細な内訳を見ることにより、各組織単位の収益性やコスト構造が明らかになり、潜んでいる課題が明確になります。
特定の部署の利益率が低い原因を特定できれば、より具体的で効果的な改善策を講じることが可能になります。
コスト削減の具体的なポイントが見つかる
企業の利益を増やすには、売上の拡大と並行してコストを適切に管理することが極めて重要です。
管理会計の手法である原価管理などを通じて、製品やサービス、工程ごとにかかる費用を細かく分析し、内訳を可視化します。
これにより、どの活動にどれだけのコストがかかっているかが明確になり、原因や削減可能な費用を具体的に特定しやすくなります。
感覚に頼ったコストカットではなく、データに基づいた合理的な削減策を実行することで、売上を維持しながら営業利益を改善することが可能となります。
社員一人ひとりに経営者意識が芽生える
管理会計によって部門ごとの目標数値や実績が全社的に共有されると、社員は自分の仕事が会社の業績にどう結びついているのかを具体的に理解できるようになります。
経理担当者だけでなく、営業や製造といった現場の社員もコストや利益を意識して日々の業務に取り組むようになり、自律的に改善を考えるきっかけが生まれます。
自分の仕事の成果が数値としてフィードバックされることで、当事者意識や経営への参画意識が高まり、組織全体のパフォーマンス向上に貢献します。
管理会計における代表的な4つの業務内容
管理会計には決まった形式はありませんが、その目的を達成するために広く用いられている代表的な業務内容や手法が存在します。
予算と実績を比較分析する「予実管理」、製品やサービスのコストを把握する「原価管理」、データから経営課題を抽出する「経営分析」、そして会社の現金の流れを管理する「資金繰り管理」がその例です。
ここでは、これらの主要な4つの業務の種類や具体的なやり方、項目、方法といった内容について解説します。
予実管理:予算と実績の差を分析する
予実管理とは、年度や半期の初めに策定した予算と、期間終了後の実績とを比較し、その差異の原因を分析する管理手法です。
単に達成・未達を確認するだけでなく、なぜ差異が生じたのかを深く掘り下げることが重要になります。
例えば、営業部門の売上予算が未達だった場合、市場の変化、競合の動向、自社の営業活動の問題など、要因を特定します。その分析結果を次の予算策定や行動計画の改善に活かすことで、目標達成の精度を高めるPDCAサイクルを回すことが予実管理の目的です。
予算管理とは異なり、分析と改善アクションまでを含む活動を指します。
原価管理:製品やサービスにかかるコストを計算する
原価管理は、製品の製造やサービスの提供にかかるコスト、すなわち原価を正確に計算し、目標内に収まるように管理する活動を指します。
特に製造業の工場などでは、製品の価格設定や利益計画の根幹をなすため非常に重要です。
事前に目標となる標準原価を設定し、実際にかかった原価との差異を分析することで、非効率な工程や材料の余剰を発見し、コスト削減につなげます。
複数の製品で共通して発生する間接費を、生産量などの適切な配賦基準を用いて各製品に割り振る、原価計算(配賦)も重要なプロセスです。
経営分析:データをもとに経営課題を洗い出す
経営分析とは、管理会計を通じて収集・整理されたデータを多角的に分析し、企業の収益性、安全性、効率性、生産性などを評価して経営課題を特定する活動です。
代表的な手法に、売上と費用が等しくなる売上高(損益分岐点)を算出し、目標利益達成に必要な売上水準を把握する、損益分岐点分析があります。これを通じて損益管理を行い、事業の採算性を評価します。
また、設備投資や新規事業の採算性を事前にシミュレーションし、投資判断の材料とすることも経営分析の重要な役割です。
資金繰り管理:会社のキャッシュフローを健全に保つ
企業経営において、利益が出ていても手元の現金が不足すれば事業継続は困難になります。
いわゆる黒字倒産のリスクを避けるため、資金繰り管理は不可欠です。
具体的には、将来の現金の収入と支出を予測した資金繰り表を作成し、キャッシュフローを管理します。売掛金の回収サイトや買掛金の支払サイトを調整し、運転資金がショートしないように常に監視することが求められます。
金融機関からの借入計画を立てる際にも、正確な資金繰りの予測が基礎となります。
安定した資金管理は、企業の信用と存続を支える土台です。
管理会計システムを導入する際の選び方
管理会計はExcelなどの表計算ソフトでも可能ですが、複雑な管理を行うには限界があるため、専用のシステムやツールの導入が効率的です。
選び方のポイントは、自社の目的に合った機能を持つシステムを選ぶことです。
クラウド型の会計ソフトやERPは中小企業でも導入しやすくなっているため、予実管理や経営分析レポートなど、自社に必要な機能や特徴を明確にして検討しましょう。
無料トライアルで操作性を試し、業種特有のテンプレートやフォーマットがあるかも確認ポイントです。
また、自社に合った作り方ができる、柔軟なひな形を持つシステムを選ぶのがおすすめです。
まとめ
本記事では、管理会計の基本的な概念から、財務会計との違い、導入の目的やメリット、さらには代表的な業務内容までを解説いたしました。
法律で定められた財務会計とは異なり、社内向けの自由な形式で経営判断に役立つ情報を生成できる点が大きな特徴です。
予実管理や原価管理、経営分析、資金繰り管理といった具体的な業務を通じて、経営状況をリアルタイムで把握し、迅速な意思決定や業績改善、目標達成をサポートします。
今回の内容をもとに管理会計を実践し、企業経営の改善を目指していきましょう。
注目のコラム記事
よく読まれている記事
新着記事
PICKUP