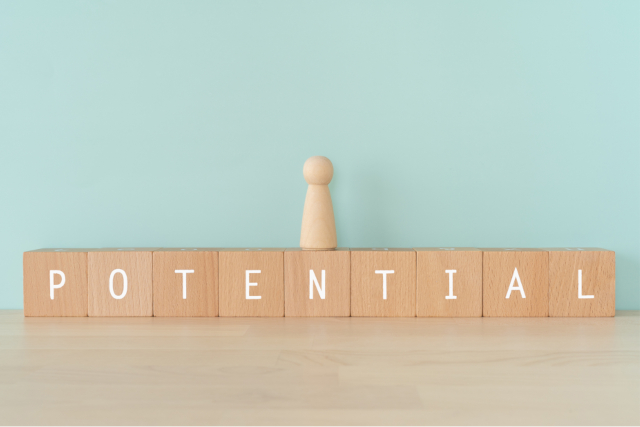2025年11月20日
カテゴリ:総務

業務の属人化とは、特定の担当者しか業務の手順や状況を把握しておらず、その情報が周囲に共有されていない状態を指します。
属人化は担当者の不在により業務が滞ったり、製品やサービスの品質にばらつきが生じたりするといったトラブルを引き起こすことがあり、多くの企業にとって解決すべき経営課題となっています。
本記事では、属人化の意味やその定義、発生するデメリット、そして属人化を防止し業務を標準化するメリットについて解説します。
INDEX
属人化の定義
属人化は、特定業務に関する手順や状況などの情報が作業担当者しか把握できておらず、周囲に共有されていない状態を指します。
これは、担当者の違いにより製品の品質に差が生じたり、担当者不在で対応方法がわからなくなったりする原因にもなります。
属人化は特定の個人に業務や知識が依存する状態であり、組織内で個人や特定のグループに業務の責任や知識が集中し、業務プロセスが依存している状態でもあります。
この状態は、組織の運営において大きなリスクを生み出すことがあります。
例えば、特定の従業員が休暇や退職した際に、業務の停滞や品質の低下が起きる可能性が高まることがリスクとして挙げられます。
また、属人化は知識が一部に集中するため、組織全体の成長や革新を阻害し、知識やノウハウの共有が困難になることも考えられます。
属人化と専門性の違い
属人化と専門性(スペシャリスト)は、ともに「特定の人が業務を行う」という点で共通していますが、その意味合いには明確な違いがあります。
属人化は、業務の進め方やノウハウが特定の担当者のみに把握され、周囲に共有されていない状態を指し、一般的にネガティブな文脈で用いられます。
属人化の場合、クローズドな環境で独自の業務進行がなされていることが多く、そこに優れた専門性が存在するとは限りません。
業務実態が見えにくいため、本来は標準化できる業務でも、専門性が高いと誤解されて属人化が進むケースもあります。
一方で、スペシャリストは特定の分野において高度な専門知識や技能を持つ人材を意味し、その専門性を活かして革新や問題解決に貢献します。
スペシャリストの業務は専門性が高くても、業務実態の可視化や共有が可能であり、知識やスキルをマニュアルや業務フローで整理し、新たなスペシャリストの育成に貢献することも期待されます。
決定的な違いは、専門性が技術力を高め、情報共有を進めることを目的とするのに対し、属人化は技術力に関わらず他者と共有できていない状態を表す点にあります。
属人化と暗黙知
属人化と暗黙知は密接な関係にあり、暗黙知が属人化を引き起こす要因の一つとなることがあります。
暗黙知とは、個人の経験や勘、ノウハウなど、言語化や可視化が難しい知識を指し、形式知の対義語です。
業務において個人の経験に基づく暗黙知が発揮されることで、他の人がその業務を遂行できない「属人化」の状態が生じる恐れがあります。
しかし、暗黙知そのものが悪いわけではありません。
むしろ、暗黙知は「特異な経験・ノウハウ・コツ」として、組織の重要な知的財産になり得るものです。
この暗黙知を言語化し、マニュアルや業務フローとして形式知へ転換することで、組織全体の知識レベルを向上させ、属人化を解消できる可能性を秘めています。
属人化の問題を解決するためには、単に個人の知識を排除するのではなく、その知識をいかに組織全体で共有し、活用していくかが重要となります。
属人化の反対概念
属人化の反対概念として「標準化」が挙げられます。
標準化とは、特定の従業員に偏っていた業務や知識を組織全体で共有し、誰もが一定水準で業務を遂行できる状態を指します。
これは「業務の最適化」とも言い換えられます。
標準化された業務は、どの担当者が関与しても同じ結果や品質を期待できる特徴があります。
また、「マニュアル化」も属人化の対義語とされており、マニュアルなどのナレッジ共有を実施することで業務を標準化することが可能です。
さらに、「平準化」という言葉も似た意味合いで使われますが、こちらは「社員ごとの負担や労力を均一にする」という意味合いが強く、属人化解消の一環として取り組まれることが多いです。
業務の標準化は、特定個人に依存しない仕組みを構築し、組織全体の業務効率や品質の向上、ノウハウの蓄積に貢献します。
属人化が生じる原因
業務が属人化する原因は多岐にわたりますが、主な原因として、業務の専門性の高さ、担当者への過度な負担、情報共有の不足が挙げられます。
業務の専門性の高さ
まず、業務の専門性が高いことが挙げられます。
高度なスキルや知識、経験が必要な業務は、対応できる人材が限られるため、特定の担当者に集中しやすく、結果として属人化が進みます。
特に中小企業では、各業務を少人数で回すことが多く、他の社員が業務内容を理解しにくい状況に陥りがちです。
担当者への過度な負担
次に、担当者が多忙であるために情報共有に手が回らないケースです。
日々の業務や目標達成に追われ、ノウハウの言語化や共有の優先度が下がってしまうことがあります。
人手不足により一人で業務をこなしている場合、情報共有の相手が見えず、業務標準化が進まず、属人化を加速させる理由となります。
情報共有の不足
また、情報共有の仕組みが整っていないことも大きな原因です。
例えば、業務フローをまとめた資料があっても、それが社員に見つけにくい場所に保存されていたり、そもそも作成されていなかったりすると、担当者以外は業務を進められなくなります。
さらに、社員が自分の地位を守りたいという意識から、意図的に業務を属人化させるケースも存在します。自分の代わりがいない状況を作ることで、社内における自身の優位性を確保しようと考えるためです。
個人成果主義が根付いている企業では、ノウハウや知識が社内競争の「武器」として扱われ、共有の文化が根付きにくく、属人化が深刻化することもあります。
レガシーシステムの影響も無視できません。老朽化・複雑化したシステムは特定の人物しか保守・運用できなくなり、業務の属人化を引き起こします。
これらの要因が単独で、または複合的に作用し、業務の属人化を招いてしまいます。
属人化がもたらす問題点
業務の属人化は、企業にとって様々なリスクと影響をもたらします。
特定の担当者に業務や知識が集中することで、組織全体の業務効率が低下したり、製品やサービスの品質にばらつきが生じたりするだけでなく、重要な知識やノウハウが失われるリスクも高まります。
さらに、管理体制や人事評価にも悪影響を及ぼし、組織の持続的な成長を妨げる要因となる可能性があります。
業務効率の悪化
属人化が進行すると、業務効率の悪化は避けられません。
特定の担当者しか業務の進め方を知らない状態では、その担当者が多忙になった場合や、急な休暇・退職などで不在になった場合に、他の社員が代わって業務を進めることができなくなり、業務が停滞してしまいます。
例えば、トラブルが発生しても担当者がいなければ対応が遅れ、解決に時間がかかることも考えられます。
これにより、特定の社員に過度な負担がかかり、長時間労働に陥りやすいという問題も生じます。
また、属人化した業務は、業務の手順や方法について客観的な評価が難しく、改善の機会を見逃しがちです。
結果として、非効率な作業がそのまま続けられ、組織全体の生産性低下を招く恐れがあります。
さらに、業務のブラックボックス化は、情報やノウハウの共有を妨げ、チーム全体の連携を困難にし、全体最適化された業務フローの構築を阻害します。
業務品質のばらつき
属人化がもたらす問題点の一つに、業務品質のばらつきがあります。
業務が特定の担当者に依存している場合、その担当者のスキルや経験、判断基準によって、提供される製品やサービスの品質が大きく変動する可能性があります。
これは、業務の手順や基準が明確に言語化・共有されていないことで、他の担当者が同じ業務を行った際に、同じ品質を維持することが困難になるためです。
例えば、顧客対応業務が属人化している場合、担当者によって顧客への説明内容や対応の質が異なり、顧客満足の低下を招く恐れがあります。
また、品質管理の観点からも問題が生じます。
特定の担当者しか業務内容を把握していないため、ミスやトラブルが発生しても、第三者によるチェックや早期発見が難しくなります。
これにより、問題が潜在化したまま進行し、後に大きな損失につながるリスクも高まります。
業務品質のばらつきは、企業のブランドイメージや顧客からの信頼を損なうだけでなく、製品やサービスの安定供給を妨げ、最終的には売上にも悪影響を及ぼす可能性があります。
知識やノウハウの喪失リスク
属人化がもたらす最も深刻なリスクの一つに、知識やノウハウの喪失があります。
特定の社員だけが業務に関する知識やノウハウを保有している場合、その社員が退職、異動、あるいは長期休暇に入った際に、これまで培われてきた貴重な情報が組織から失われてしまう可能性があります。
これは、まるで「個人の頭の中に会社の財産が詰まっている」ような状態であり、企業にとって計り知れない損失をもたらすことになります。
例えば、営業担当者が顧客との長年の関係の中で築き上げたノウハウや、技術者が試行錯誤の末に生み出した独自の解決策などが、後任者に適切に引き継がれずに失われると、業務の再現性が著しく低下し、最悪の場合、ビジネス機会の喪失や競争力の低下につながることも考えられます。
特に、専門性の高い業務や、長年の経験が不可欠な業務においてこのリスクは顕著です。
知識が共有されないことで、新たな人材の育成も困難になり、組織全体の成長を阻害する要因ともなります。
知識やノウハウの喪失を防ぐためには、属人化を解消し、これらの情報を組織の共有財産として蓄積し、活用できる仕組みを構築することが不可欠です。
管理体制への影響
属人化は、企業の管理体制にも多大な影響を及ぼします。
特定の個人に業務が集中し、その内容や進捗がブラックボックス化すると、管理者は業務全体の状況を正確に把握することが困難になります。
これにより、適切なリソース配分や人員計画が立てづらくなるだけでなく、業務のボトルネックが発生しても早期に発見し、改善策を講じることが難しくなります。
また、品質管理の観点からも問題が生じ、担当者の業務が適切に行われているか、品質基準が守られているかを確認する術が限られるため、一貫性のない業務遂行や品質低下のリスクが高まります。
さらに、業務の透明性が失われることで、不正やミスの発生を見逃しやすくなる可能性も指摘されています。
管理者が業務の詳細を把握できない状況では、内部統制が機能しにくくなり、コンプライアンス違反のリスクも増大します。
結果として、組織全体のガバナンスが揺らぎ、経営判断にも悪影響を及ぼす恐れがあるため、属人化はマネジメント上の喫緊の課題として認識すべきです。
人事評価の難しさ
属人化は人事評価のプロセスにおいても課題を生じさせます。
特定の社員しか業務の詳細を把握していない状態では、上司や評価者がその業務の具体的な内容、プロセス、成果を正確に評価することが極めて困難になります。
業務がブラックボックス化しているため、担当者の貢献度や業務遂行能力を客観的な基準で測ることが難しく、結果として適正な人事評価が行えない可能性が高まります。
例えば、担当者の仕事の進め方が非効率であったり、品質に問題があったりしても、他の誰もその状況を把握できないため、適切なフィードバックや改善指示を与えることができません。
これにより、担当者は自身の業務における課題を認識しにくくなり、成長の機会を失うことにもつながります。
また、公平な評価が行われないことは、社員のモチベーション低下や不満の原因となり、組織全体のエンゲージメントにも悪影響を及ぼす可能性があります。
属人化された業務における人事評価の難しさは、結果的に組織全体の健全な人材育成と成長を阻害することにつながるため、早急な対策が求められます。
属人化を避けるべき業務
属人化は多くのリスクを伴うため、特定の業務においては積極的に回避すべきです。
再現性が求められる業務、継続性が重要な顧客対応業務、重大な影響を持つ対応業務は、属人化が進むと企業に深刻なダメージを与える可能性があります。
これらの業務では、誰が担当しても一定の品質と迅速な対応が保証されるよう、業務の標準化とナレッジ共有が不可欠となります。
再現性が求められる業務
再現性が求められる業務は、特に属人化を避けるべき業務の典型です。
これらの業務は、誰が担当しても同じ手順、同じ品質で遂行できることが必須であり、担当者によって結果が異なるようでは、企業全体の信頼性や生産性に直結する問題となります。
例えば、バックオフィス業務における契約書処理、請求書の発行、在庫管理・発注などは、その性質上、常に正確性と一貫性が求められます。
もしこれらの業務が特定の社員に属人化していると、その社員が不在になった際に業務が滞るだけでなく、処理の抜け漏れやミスが発生しやすくなり、企業の運営に大きな支障をきたす可能性があります。
また、マニュアルが存在しなかったり、存在しても更新されずに古い情報であったりする場合、新人が業務を引き継ぐ際の教育コストが増大し、早期の戦力化が困難になります。
再現性が重視される業務では、業務フローの明確化、マニュアルの整備、そして定期的な見直しと改善を通じて、特定の個人に依存しない仕組みを構築し、誰でも滞りなく対応できる体制を確立することが、リスク回避と効率化のために不可欠です。
継続性が重要な顧客対応
継続性が重要な顧客対応業務は、属人化を避けるべき筆頭の業務です。
営業やカスタマーサポートなど、顧客と直接関わる業務において、特定の担当者のみが顧客情報や対応履歴、関係性を把握している状態は、非常に大きなリスクを伴います。
顧客は特定の担当者との間に信頼関係を築いていることが多いため、その担当者が急に不在になった場合、顧客は不安を感じ、不信感を抱く可能性があります。
例えば、担当者が休暇中であったり、異動や退職してしまったりすると、他の社員が顧客からの問い合わせに対応する際に、これまでの経緯が分からず、適切なサービスを提供できない事態が生じます。
これにより、顧客満足度の低下や機会損失、最悪の場合は顧客の離脱につながる恐れがあります。
また、人によって説明内容やサービスレベルが異なるという状況は、企業のブランドイメージにも悪影響を及ぼします。
継続性が求められる顧客対応業務においては、顧客情報を一元的に管理し、対応履歴やノウハウをチーム全体で共有する仕組みを構築することが不可欠です。
これにより、誰が対応しても一貫した高品質なサービスを提供できるようになり、顧客との長期的な信頼関係を維持・強化することができます。
重大な影響を持つ対応業務
重大な影響を持つ対応業務も、属人化を避けるべき重要な業務の一つです。
これらの業務は、誤った判断や対応の遅れが企業に甚大な損害を与える可能性があるため、特定の個人に依存した状態は極めて危険です。
例えば、システムトラブルやセキュリティインシデントへの対応は、まさにこれに該当します。
トラブル発生時には迅速かつ正確な初動対応が不可欠であり、担当者が不在であったり、対応方法が属人化していたりすると、被害が拡大するリスクが高まります。
情報漏洩やシステム停止など、一度発生すると企業の信頼失墜や事業継続に関わる重大な影響を及ぼす可能性があります。
また、製品の品質問題や顧客からの重大なクレーム対応なども、適切な手順と組織的な連携が求められる業務です。
特定の担当者しか対応方法を知らない場合、適切な判断が遅れたり、問題が隠蔽されたりするリスクも生じます。
これらの業務においては、緊急時対応フローの確立、リスクマネジメント体制の強化、そして複数人での知識共有と対応訓練を徹底することで、属人化のリスクを軽減し、有事の際に組織として迅速かつ的確に対応できる体制を構築する必要があります。
属人化が有利に働く場面
属人化は一般的にデメリットが多いとされますが、特定の状況下では有利に働くこともあります。
例えば、新規事業の立ち上げや、前例のない複雑な問題解決など、高度な専門性と柔軟な判断が求められる業務においては、特定のスペシャリストがその能力を最大限に発揮することで、迅速かつ高品質な成果を生み出すことが可能です。
このような場面では、個人の裁量が大きく、試行錯誤を通じて新たなノウハウが生まれることも期待できます。
また、顧客との長期的な信頼関係が構築されている営業やコンサルタント業務などでは、特定の担当者が一貫して対応することで、顧客満足度を高めることにもつながります。
さらに、小規模なプロジェクトや短期間のミッションにおいては、情報共有やマニュアル作成にかかるコストを削減し、迅速に業務を遂行できるという側面もあります。
ただし、これらのメリットを享受しつつも、将来的なリスクを考慮し、いざという時には対応できるような最低限の知識共有やバックアップ体制を検討することも重要です。
業務の標準化が求められる背景
業務の標準化が近年、多くの企業で求められている背景には、いくつかの重要な要因があります。
まず、日本の深刻な人材不足と、それに伴う人材の流動化の進展が挙げられます。
安定的な人材確保が困難な状況において、特定の個人に業務が集中する属人化は、その人材が退職したり休職したりした場合に、業務が滞る大きなリスクとなります。
業務を標準化することで、誰が担当しても一定の品質を保って業務を遂行できるようになり、人材の入れ替わりや多様な働き方にも柔軟に対応できる体制を構築できます。
次に、グローバルな視点での競争力獲得の必要性です。
国際競争が激化する中で、企業は生産性の向上と品質の安定化を追求する必要があります。
業務を標準化し、平準化することで、拠点間の認識のずれをなくし、組織全体で効率的な業務運営が可能になります。
これは、新しいルールを迅速に浸透させたり、余剰となった人的リソースを他の部署や業務に再配置したりする際にも有効です。
属人化を解消し業務を標準化する方法
属人化を解消し、業務を標準化するためには、体系的なアプローチが不可欠です。
まず、現状の業務内容を正確に把握し、何が属人化しているのかを明確にすることから始めます。
次に、その中で優先的に改善すべきプロセスを選定し、具体的な業務手順の整備とマニュアル化を進めます。
これらの取り組みは一度行えば終わりではなく、継続的な見直しと改善を繰り返すことで、実効性の高い標準化を実現できます。
このプロセス全体を通して、ITツールの活用も非常に有効な手段となります。
適切なツールを導入することで、情報共有の促進、業務の可視化、そして効率的なマニュアル作成・管理が可能になり、属人化による負担を軽減し、組織全体の業務効率と品質向上に貢献します。
現状の業務内容の把握
属人化を解消し、業務を標準化するための最初のステップは、現状の業務内容を正確に把握することです。
これは、組織内のどの業務が属人化しており、どのような課題を抱えているのかを「可視化」するプロセスです。
具体的には、まず業務フローを可視化することから始めます。
各業務が誰によって、どのような手順で、どれくらいの時間をかけて行われているのかを詳細に洗い出します。
この際、口頭で伝えられているだけの「暗黙知」となっている部分や、特定の担当者しか知らない「ブラックボックス化」したノウハウを顕在化させることが重要です。
ヒアリングやアンケートを通じて、担当者から直接情報を収集するだけでなく、実際に業務現場を観察し、記録することも有効な手段となります。
マニュアルが存在しない業務や、マニュアルが古いために実態と乖離している業務、特定の担当者に負荷が集中している業務などは、属人化の兆候である可能性が高いと判断できます。
これらの情報を体系的に整理し、文書化することで、現状の業務における課題や非効率な点を客観的に把握し、次のステップである改善対象プロセスの選定へとつなげることができます。
改善対象プロセスの選定
現状の業務内容を把握し、属人化している業務が可視化されたら、次にどのプロセスから改善に着手するかを選定します。
全ての属人化された業務を一気に解消しようとすると、リソースが不足したり、現場の負担が大きくなったりして、かえって混乱を招く可能性があります。
そのため、優先順位をつけて取り組むことが重要です。
改善対象プロセスの選定においては、以下のような観点を考慮すると良いでしょう。
まず、「緊急度と重要度」です。
担当者の不在時に業務が完全に停止してしまうなど、事業継続に大きな影響を与える業務は優先度が高くなります。
次に、「影響範囲の大きさ」です。
特定の業務が属人化していることで、他の部署や顧客にも大きな影響が及ぶ場合は、早急な対応が求められます。
また、「標準化の難易度」も考慮すべき点です。
複雑性の高い業務や、高度な判断が求められる業務は標準化に時間がかかるため、比較的標準化しやすい業務から着手することで、成功体験を積み、その後の取り組みにつなげることができます。
さらに、「担当者の意欲」も重要な要素です。
担当者が属人化解消に協力的である業務から始めることで、スムーズな情報共有やマニュアル作成が期待できます。
これらの観点から総合的に判断し、最も効果的かつ実現可能性の高いプロセスを選定することが、属人化解消に向けた取り組みを成功させる鍵となります。
業務手順の整備とマニュアル化
改善対象とする業務プロセスが選定されたら、次はその業務手順を詳細に整備し、マニュアル化を進めます。
この段階が、属人化を解消し、業務を標準化するための核心的なステップです。
まず、現状の業務フローを詳細に分析し、無駄な工程や重複している作業がないかを確認しながら、最適な手順を定義します。
この際、実際に業務を担当している社員の意見を積極的に取り入れ、現場の実態に即した内容にすることが重要です。
次に、定義した業務手順を明確な言葉で記述し、視覚的に分かりやすい図や画像、動画なども活用しながらマニュアルを作成します。
マニュアルは、誰が読んでも同じように業務を遂行できるレベルの具体性が必要です。専門用語の使用は避け、初心者でも理解できるように平易な言葉で説明することを心がけます。
また、業務で得られたノウハウやイレギュラーなケースへの対応方法なども盛り込むことで、より実用性の高いマニュアルとなります。
継続的な見直しと改善
属人化を解消し、業務を標準化する取り組みは、一度マニュアルを作成して終わりではありません。
重要なのは、その効果を継続的にモニタリングし、必要に応じて見直しと改善を繰り返していくことです。
業務環境や組織体制は常に変化するため、作成したマニュアルや標準化したプロセスが陳腐化する可能性があります。
例えば、新しいツールの導入、法改正、顧客ニーズの変化などがあった場合、それらに合わせて業務手順やマニュアルも更新していく必要があります。
定期的に業務フローが最適化されているか、マニュアルが実態に即しているかを確認し、課題があれば改善策を講じることが重要です。
また、実際にマニュアルを活用している社員からのフィードバックを積極的に収集し、内容の分かりにくかった点や、追加すべき情報がないかなどを洗い出すことも有効です。
ジョブローテーションの実施も、標準化された業務が定着しているかを確認し、属人化の再発を防ぐための効果的な手段となります。
異なる担当者が業務を行うことで、マニュアルの不備や改善点が見つかりやすくなるだけでなく、新たなノウハウが生まれ、それをマニュアルに反映させることで、組織全体の知識レベルを向上させることにもつながります。
このように、継続的な見直しと改善を通じて、業務標準化のPDCAサイクルを回し、属人化を常に解消し続ける体制を構築することが、企業の持続的な成長には不可欠です。
属人化解消に貢献するITツール
属人化を解消し、業務を標準化する上でITツールの活用は非常に有効です。
これらのシステムは、情報共有の促進、業務プロセスの可視化、ノウハウの蓄積・活用を効率的に支援し、担当者の負担を軽減する役割を果たします。
具体的には、ナレッジマネジメントツール、ワークフローシステム、プロジェクト管理ツール、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)、そしてマニュアル作成ツールなどが挙げられます。
これらのツールを導入することで、これまで個人の頭の中にあった知識や経験が組織全体で共有され、誰でも必要な情報にアクセスできるようになります。
これにより、業務のブラックボックス化を防ぎ、品質の安定化や効率化を実現し、属人化のリスクを大きく軽減することが期待できます。
導入の際には、自社の業務内容や課題に合ったツールを選定し、社員が活用しやすいよう適切なトレーニングとサポートを提供することが成功の鍵となります。
まとめ
属人化は、特定の担当者しか業務内容やノウハウを把握していない状態であり、業務効率の悪化、品質のばらつき、知識喪失のリスクなど、企業に多くの問題をもたらします。
これを解消し、業務を標準化することは、人材不足や多様な働き方が進む現代において、企業の持続的な成長に不可欠です。
本記事で解説した属人化を解消するための手順や、有効なITツールを活用することで、組織全体の生産性向上とリスク軽減が実現できます。
注目のコラム記事
よく読まれている記事
新着記事
PICKUP